授乳中に脱毛はNG?再開のタイミングと合わせて解説!ー福岡・沖縄の医療脱毛ならKANNO'A.clinic(カノアクリニック)

出産を経て「そろそろ脱毛を再開したい」と考える方も多いのではないでしょうか。しかし、授乳中はホルモンバランスが不安定で、肌や毛の状態にも変化が起こりやすい時期。医療脱毛を受ける前に、授乳中に避けたほうがいい理由や再開のベストタイミングを知っておくことが大切です。
ここでは、授乳中に脱毛を控えるべき理由と、安心して再開できるタイミングを詳しく解説します。
<目次>
授乳中に脱毛はNG?その理由は?
授乳中は、ホルモンバランスや体調が大きく変化するため、医療脱毛の施術は基本的に控えるのが安全です。
レーザー脱毛が母乳や赤ちゃんに直接影響を与えることはありませんが、薬の服用制限・体力低下・ホルモンの変動など、複数の要因によって肌トラブルのリスクが高まります。
また、授乳中は睡眠不足やストレスで免疫力も下がりやすく、肌の回復が遅れる傾向があります。安全かつ確実な脱毛効果を得るためには、授乳が落ち着き、ホルモンバランスが安定してからの再開がおすすめです。
万が一の時に服用できる薬が少ないから
授乳中は、母乳を通じて赤ちゃんに薬の成分が移行する可能性があるため、服用できる薬が非常に限られています。医療脱毛の施術後に炎症や赤みが出た場合、本来なら抗炎症薬や抗生物質で治療しますが、授乳中はそれが難しいのです。このため、トラブル発生時に十分な対応ができないリスクがあります。
母体と赤ちゃんの安全を第一に考え、授乳期間中は施術を控える判断が推奨されています。
育児の疲れや授乳で体力が低下しているから
授乳期のママは、寝不足や栄養不足が続き、体力が低下しやすい時期です。さらに、母乳を作るために体内の栄養やエネルギーが使われるため、肌の回復力が落ちやすく、乾燥や炎症が起こりやすい状態になります。
このような状態でレーザーを照射すると、色素沈着や肌荒れなどのトラブルを起こすリスクが高まります。安全に施術を受けるためには、体調が安定し、十分に休息が取れるようになってからの再開がおすすめです。
ホルモンバランスが通常時とは異なるから
授乳中は、母乳を分泌するためのプロラクチンというホルモンが多く分泌されています。このホルモンは毛周期にも影響を与え、毛の生え変わりリズムが不安定になります。そのため、レーザー照射を行っても毛根が反応しにくく、脱毛効果を感じにくいケースがあります。
また、ホルモンバランスの変化によって肌が敏感になり、施術後の赤みやヒリつきが出やすい時期でもあります。ホルモンの働きが安定してから再開した方が、肌への負担も少なく、効果的な脱毛が期待できます。
多毛症になっていると効果が出にくい可能性がある
出産や授乳の影響で、一時的に体毛が濃くなる「多毛症」状態になることがあります。この時期は毛周期が乱れており、レーザーを照射しても十分に反応しないことがあります。
ホルモンが落ち着いたタイミングで施術を再開することで、より安定した脱毛効果が得られます。
授乳中でも脱毛できるサロンの利用は注意が必要!

授乳中はホルモンバランスの変化や体調の揺らぎが大きく、肌がとてもデリケートな時期です。普段は問題なく受けられる脱毛施術でも、刺激を強く感じたり、肌トラブルが起こることがあります。そのため、授乳中に脱毛を検討する際は、まず産科(産婦人科)に相談することが大切です。医師の判断をもとに安全なタイミングを確認し、自分の体調に合った方法を選びましょう。
また、クリニックで施術を受けた場合でも、授乳中は服用できる薬が限られているため、万が一トラブルが起きた際に十分な治療が行えない可能性があります。こうしたデメリットを理解したうえで、施術を慎重に検討しましょう。
ここでは、授乳中に脱毛を受ける際に注意したいポイントを紹介します。
① 肌が敏感になりやすく刺激を受けやすい
授乳中はホルモンの影響で肌のバリア機能が低下し、赤み・かゆみ・炎症などが出やすくなります。脱毛の光やレーザーの刺激で、通常よりも痛みを感じたり、施術後に肌荒れが起きたりすることもあります。施術を受ける際は、必ず肌の状態をスタッフや医師に伝えるようにしましょう。
② 体調やホルモンの変化で効果が不安定に
授乳中はホルモンバランスが通常とは異なり、毛周期や発毛状態にも変化が出ることがあります。そのため、施術を受けても効果が出にくかったり、ムラが生じたりするケースもあります。産後の体が安定してから再開した方が、より高い効果を得られるでしょう。
③ 使用されるジェルや薬剤にも注意
脱毛の施術中やアフターケアにはされるジェルや鎮静クリームが使用される場合があります。これらの中には、防腐剤や冷却成分が含まれる場合があります。これらが授乳中の体や赤ちゃんに影響するリスクは低いですが、完全に安全とはいえません。気になる方は、無添加タイプの使用可否を事前に確認しておくと安心です。
④ トラブル対応ができる環境を選ぶ
施術後に炎症ややけどなどが起きた場合、すぐに医師の診察を受けられる環境を選ぶことが重要です。医療従事者が常駐するクリニックであれば、肌トラブル時にも迅速な対応が可能です。
脱毛はいつ頃再開できるの?
出産や授乳を経たあとの脱毛再開は、体の回復状況やホルモンバランスの安定度によって個人差があります。目安としては、授乳が落ち着き、月経が再開してホルモンバランスが整ってからがおすすめです。
再開の目安は「授乳終了後+体調が安定してから」
授乳を終えてから少なくとも1?2か月ほど経過し、体調やホルモンバランスが整ってから脱毛を再開するのが理想です。授乳中はホルモンの変動により毛周期が乱れやすく、施術を受けても十分な効果が得られない場合があります。ここでは、再開の目安をより詳しく解説します。
授乳後1?2か月は肌と体の回復期間
授乳が終わっても、体の中ではまだホルモンが変化している最中です。出産や授乳で消耗した体力を取り戻し、肌の乾燥や敏感さが落ち着くまでには時間がかかります。
ホルモンバランスが整ってからの再開が安全
授乳中は女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の分泌が不安定で、毛周期にも乱れが生じます。ホルモンが安定してくると毛の生え変わりのリズムも整い、脱毛効果をしっかり実感しやすくなるため、焦らず体の回復を優先させましょう。目安としては、生理が再開してから1?2周期ほど経過した頃がおすすめです。
睡眠や栄養状態もチェック
産後は睡眠不足や栄養不足により、肌トラブルが起きやすい時期でもあります。疲労が蓄積していると、施術時に痛みを感じやすくなったり、照射後の炎症や色素沈着のリスクが高まることも。しっかり眠れて、食事からエネルギーが取れている状態になってから再開するのが安心です。
再開前には医師への相談を
「もう大丈夫かな」と思っても、自己判断での再開は避けましょう。必ずかかりつけの産科(産婦人科)や脱毛クリニックの医師に相談し、体調・肌の状態を確認してもらうことが大切です。特に授乳中は、トラブルが起きた際に使える薬が限られるため、医師の判断をもとに安全なタイミングを見極めてください。
授乳中でも可能なムダ毛の自己処理方法

授乳中は肌が敏感で、脱毛施術を受けられないこともあります。そんな時は、肌に負担をかけない範囲での**セルフケア(自己処理)**がおすすめです。ここでは、授乳中でも安心して行えるムダ毛ケアのポイントを紹介します。
① 電動シェーバー
授乳中の肌は刺激に弱いため、カミソリよりも電動シェーバーを使うのが安心です。刃が直接肌に当たらない構造なので、カミソリ負けや小さな傷のリスクを軽減できます。使用前後には、清潔な刃を使うことと、処理後の保湿ケア(低刺激タイプの乳液など)を忘れずに行いましょう。
除毛クリームは手軽ですが、化学成分による刺激が強いため、授乳中の敏感肌には向かないことがあります。電動シェーバーなら、肌に負担をかけずに自己処理をすることができます。
②毛抜き・ワックスは避ける
毛抜きやワックスは毛根ごと抜くため、炎症や埋没毛が起こりやすく、授乳中の不安定な肌には不向きです。感染リスクもあるため、授乳中の敏感な肌に使用するのはやめておきましょう。
③ 自己処理後のスキンケアも大切
自己処理後の肌は非常に乾燥しやすい状態です。刺激の少ないセラミド・ヒアルロン酸配合の保湿剤を使い、肌のバリア機能を整えましょう。また、処理直後の入浴や日焼けは避け、肌が落ち着くまで数時間あけるのがベストです。
④肌トラブルがある場合は自己処理を控える
ニキビ・湿疹・赤みなどがある部分は、処理によって悪化することがあります。その場合は無理をせず、皮膚科で相談してください。状態によっては、授乳中でもおこなえる肌トラブルのケア方法を提案してもらえることもあります。
授乳期間も加味したクリニックを選ぼう
授乳中に脱毛を検討する際は、肌の状態だけでなく「ライフステージに合わせた通いやすさ」を重視することが大切です。ホルモンバランスや生活リズムが変わりやすい時期だからこそ、柔軟な対応をしてくれるクリニックを選びましょう。
① 授乳中の施術可否を明確にしているか
まず確認したいのは、授乳中でも施術が可能かどうかです。クリニックによって方針が異なり、「授乳中は全ての部位が対象外」「体調や医師の判断で一部照射可」などさまざまです。
この点を曖昧にせず、カウンセリングの段階で「どの条件なら施術できるか」を明確に説明してくれるクリニックを選びましょう。授乳中はホルモンの影響で肌が敏感になりやすいため、医師が常駐し、安全性を確認してくれる環境が理想です。
② 妊娠・出産による休会制度があるか
脱毛は数か月~数年かけて通う長期的な施術です。そのため、妊娠・出産・授乳などで一時的に通えなくなった場合に休会できるかどうかを確認しておきましょう。
休会制度があるクリニックなら、出産や育児期間中に通院をストップしても契約が無効にならず、再開時に残り回数を引き続き利用できます。制度がない場合は、再契約や追加料金が必要になることもあるため、契約前に必ずチェックしておくのが安心です。
③ 契約期限がある場合の対応を確認
多くのクリニックでは、契約に有効期限(例:2年~3年)が設けられています。妊娠・出産で通えない期間がある場合、その間も期限が進行してしまうケースがあります。
契約前に、「妊娠・授乳を理由に期限の延長ができるか」「再開時の取り扱い」について確認しておくと安心です。柔軟に対応してくれるクリニックなら、無理に通う必要がなく、体調が整ってから再開できます。
④ カウンセリングで授乳中と伝える
カウンセリングでは、必ず「授乳中であること」や「出産直後であること」を正直に伝えましょう。医師や看護師がその情報をもとに、安全な部位・施術時期・照射レベルを調整してくれます。
授乳中であることを伝えずに施術を受けると、薬や照射設定などに制限があるにもかかわらず、リスク説明を受けられない可能性もあります。安全のためにも、最初にしっかり共有することが大切です。
まとめ
授乳中はホルモンバランスの変化で肌が敏感になり、トラブルが起きやすい時期です。無理に脱毛を行うより、まずは産科(産婦人科)で相談し、医師の判断をもとに再開時期を見極めましょう。
授乳中は使用できる薬が限られるため、万が一の際に十分な処置が難しい場合もあります。体調やホルモンが安定してから再開することで、より安全に効果を実感できます。妊娠・出産による休会制度や契約延長があるクリニックを選ぶと安心です。
天神・博多・小倉・那覇に展開するKANNO'A.clinic(カノアクリニック)では、医療従事者が常駐し、産後・授乳中の患者様にも安心してご相談いただける体制を整えています。
お肌や体調の状態を丁寧に確認したうえで、安全性を最優先にした医療脱毛をご提案しています。
さらに、KANNO'A.clinicでは、妊娠された場合は無料で休会制度を利用でき、その期間分は契約期限が延長されるため、ライフイベントの変化があっても安心して通い続けられます。
授乳後に脱毛を再開したい方や、妊娠中に今後のプランを相談したい方も、ぜひ一度KANNO'A.clinicの無料カウンセリングへご相談ください。


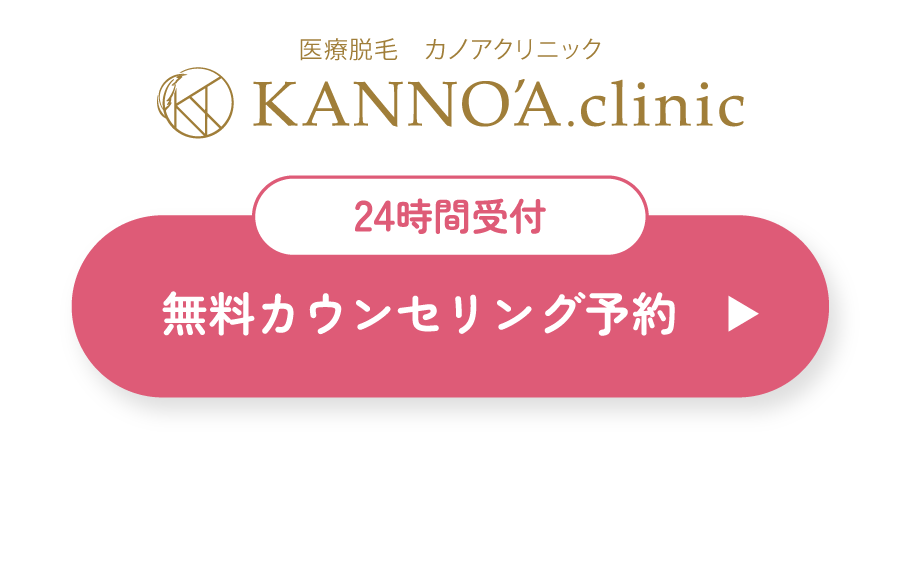

美容医療において大事なことは患者様にご満足頂き、皆様の生活の質を向上させることは勿論のこと、安全に医療を提供することだと思います。
今まで培ってきた形成外科医としての専門知識と技術を生かし、皆様に安心して受診して頂けるクリニックを目指しております。
まずはお気軽にご来院下さい。
皆様のご来院を心よりお待ちしております。
◆資格・所属学会
日本形成外科学会 専門医/日本美容皮膚科学会 正会員/日本創傷外科学会 正会員/日本形成外科手術手技学会 正会員/日本医学脱毛学会(医師会員)/歯科医師免許